2024 12/10 国立台湾大学台湾文学研究所の学生との共同授業
2024年12月3日、10日(両日とも15:10-16:40)の2回にわたり、オンラインにて国立台湾大学台湾文化研究所の学生と共同授業を行いました。
第1回の12月3日には、大阪大学の学生10名が2班に分かれ、日本の国語教育に関する発表を行いました。
第1グループは、日本の小学校国語における物語教育に着目した発表でした。文部科学省の三大教育支柱や学習指導要領等の方針を参照しつつ、物語『ごんぎつね』の現場の教育事例を踏まえ、結論として教師が特に文章中の登場人物の心情の変化を生徒に想像させることを重視しており、児童も比較的多くの時間をかけて考え、自分が気付いた登場人物の変化を発表していることが述べられました。
第2グループは、日本の古典教育に注目し、日本の古典教育の開始時期に関して対立した意見があることを紹介しました。また、日本の古典教育の問題点についても言及し、段階的な教育を行うことや、学生が主体的に学習するようなディスカッションや創作活動等をより積極的に授業に取り入れることが提案されました。さらに、古典教育は試験のためという目的に留まるべきでなく、伝統文化や知識を学ぶ機会でもあるべきだと主張されました。

第1回目(12月3日)の様子
第2回となる12月10日には、国立台湾大学の学生5名が台湾と日本に関する3つのテーマの発表を行いました。
第1グループは、台湾文学中の日本語の混用に注目し、混用が見られる作品の背景として、日本統治時代の日本語教育を受けた筆者によるもの、1987年以降に日本統治時代を題材としたもの、「台湾語の発音の日本語」が書かれたものなどがあると紹介されました。張文薫副教授からは、日本語世代の作家にとって日本語は母語であるが、それ以降の世代の作家にとっては母語ではなく、より意識的に混用しているため、日本語混用と言っても意味合いが違う、と補足解説がありました。
第2グループは、台湾での会話中での日本語の混用に注目しました。第1グループとの違いとして1990年代末の「哈日」現象で、台湾人の日本の漫画、アニメや映画に対する関心が急激に高まり、日常生活の中に日本の文化に関連した単語が使われるようになった点が挙げられました。さらに、日本語世代の台湾人と1990年代の「哈日族」が使っていた日本語の語彙について紹介があり、また、2000年代以降のACG文化や、2010年以降に日本旅行の流行やオンライン交流が身近になったことも後押しし、若者やネット世代は日本語の語句を使うことにより慣れていったという歴史的な展開にも言及がありました。最後に、日本語と台湾語の関係性についての説明がありました。
第3グループは、台湾と日本、香港の中学校の国語教科書に注目した発表でした。まず、台湾と香港の国語の教科書の比較分析が行われました。比較のなかで、台湾側の古典作品が少なくなったこと、台湾と香港の「指定範文(国語教科書に必ず入れなければならない文学作品)」、台湾と香港の古典の特徴(台湾の古典散文が盛り込まれており、香港の教科書には唐詩や宋詩が含まれている)などが述べられました。次に、台湾と日本の国語教科書の比較分析が行われました。必修/選択科目の別や近年の台湾の国語教科書改革の紹介があり、改革の紹介では、1つ目に美観(見た目の美しさ)、2つ目に章立ての工夫が挙げられ、日本の状況と比較すると興味深いものでした。
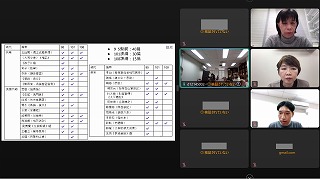
第2回目(12月10日)の様子
全2回の共同授業を通して、今まで以上に日台それぞれの文化や関係性を知ることができ、充実した取組みとなりました。